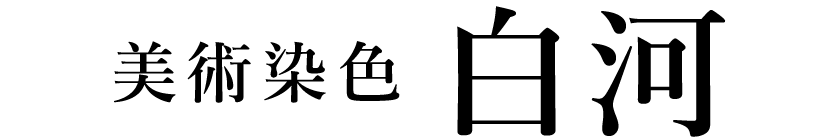大蔵流狂言 善竹忠重先生から
素襖(すおう)の制作依頼を
承りました。
今回の制作は写しではなく
完全なオリジナルの新作です。
生地は五郎丸という富山県で
織られた国産の麻布を
使用して染めることにしました。
誰も見たことのない
新しい素襖の世界を目指しての
制作となりました。
仕上がりが良ければですが、
文化財にもなる可能性もあるので
身の引き締まる思いで
制作に挑みました。
今回の素襖の制作は
特に、あらすじを踏まえての
制作をすることが必要でした。
演目は「花子」です。
大蔵流には大切な決まりごとがあり、
伝統を重んじ、
あらすじを踏まえて
図案を描くことにしました。
先ず、奈良の春日大社の藤の写生を
いっぱいしました。
この写生を基に原寸大の紙に
図案を描きました。
更に藤、八つ橋、流水文様、
雲を描き出しました。
素襖は上下弐部に分かれており
其々に図案を描きました。
袴には谷折り山折りの寸法に
決まりごとがありまして、
原寸大の図案紙では山折りの線を青で、
谷折りの線を赤で描いて目印としました。
袴は足を開いたときに襞(ひだ)の
奥からチラリと見える模様と、
脚を揃えて立った時の
模様の見え方を考えて、
どちらでも格好よく決まる配置に
工夫を要しました。
それから着用した時の上下の模様の
一帯感と連続性を考慮して
配置を決定しました。
花子のあらすじは皆様ご存知のように、
男が赴任先から帰国途中に
美濃(現在の岐阜県)あたりにいた
白拍子(遊女)と
仲良くなってしまいました。
男は都に帰らなければならないと言って
花子を残して妻のいる自宅へと
帰ってしまうのです。
その後、都まで追ってきた花子から
男に「会いたい」と手紙がきました。
この男の妻は、焼きもち焼きでして
妻の目を盗んで花子に会いに行きたい男は
一計を案じて、
妻に自分はこれから
坐禅衾(ざぜんぶすま)を被って
持仏堂に籠り
一晩中、座禅をするので、
絶対に見に来ないように
と言い残して
花子に会いに行ってしまいます。
実は持仏堂には太郎冠者が
身代わりとなって座禅衾を被って
座っています。
やきもち焼きの妻の直感か、
どうも怪しいと思い持仏堂を見に行くと
太郎冠者が身代わりとなっていることが
分かってしまいます。
真相をつきとめた妻は
自ら座禅衾を被って
太郎冠者になりすまし、
虎視眈々と待ち構えています。
そこに男が上機嫌で帰ってきます。
男は座っているのが
太郎冠者だと思い込んでいるので、
花子との楽しかった一夜を
語ってしまいます。
ちょっと変だなと感じた男が
座禅衾を取り去ると、
そこには妻が・・・
怒り狂う妻に追いかけられて
逃げ惑うという。
話なので、こういったあらすじをふまえ、
話の前半では、
遊女が惚れるような男性に見える
装束にしなければなりません。
現代なら、さしずめ色男ぶりが上がる、
ハイブランドのお洒落なスーツでしょうか。
とにかく若々しくて
カッコいい男性に見えるように
地色や模様を工夫しました。
男が颯爽と登場する最初の場面では
橋掛かりを歩く姿がカッコよく見えるように
特に演者の右側の模様の位置や密度、
大きさを工夫しました。
また袴の流水模様にも
独自の一工夫を加えました。
それは男が花子に会いに行ったのが
夜なので、
袴の裾の上を向いている
流水模様の一部分に満月が
写り込み乱れている様を描きました。
話の後半、
ことが終わって男が帰宅する場面では、
この丸い流水模様は
朝の太陽が写っているように
解釈を変えて見えるように
仕組んであります。
これは日本の伝統芸能に見られる
見立てという考え方を取り入れたわけです。
話の後半で片袖を脱いで
肩に掛けて再登場する場面では、
なんとも間抜けで、
ちょっとユーモラスな男に見えるようにと
考えて模様を配置しました。
この素襖には、
ひとつの装束の中に二つの人格と、
夜から朝へと流れる時間経過を
併存させる面白さがあり
今回の素襖制作を通じて
日本の伝統芸能の奥行の深さを
見た感じで
感銘を受けることになりました。
このようにして、ようやく完成した素襖は
地色の染めとロウケツ染めの工程だけでも
5か月を要し、更に写生や下絵制作を
含めると、
ほぼ1年かかりの制作となりました。
そして、この素襖は大阪の能楽堂にて
満員の観客の前での初披露となり
喝采を浴びました。
制作者である私の名前も
舞台からご紹介頂き恐縮しました。
善竹忠重先生の演じる花子は
とてもカッコよくチャーミングでした。
染色は日本の伝統芸能に支えられて
発展してきたのだと、
その歴史にあらためて感謝をしました。
これからも狂言の益々の
ご発展をお祈り申し上げます。